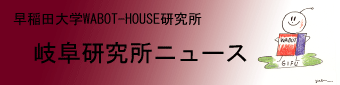
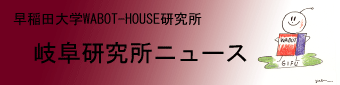
メールニュース第2号の内容をお知らせします。
購読希望の方はmailnews_admin@wabot-house.waseda.ac.jpからお申し込みください。
【早稲田大学WABOT-HOUSE研究所 メールニュース 第2号】
2004.01.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新の情報についてはhttp://www.wabot-house.org/をご参照下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《MENU》
●ご挨拶
●展示・出版・催しなどのお知らせ
●岐阜研究所ニュース 12月トピックス
●WABOT−HOUSEコラム
●リンク集<第二回・ロボット関連>
●編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
《ご 挨 拶》
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
皆様、明けましておめでとうございます。
新年も早稲田大学WABOT-HOUSE研究所を宜しくお願い致します。
早稲田大学WABOT-HOUSE研究所メールニュース第2号をお届けします。
今号より坂本義弘助手による「知能ロボティクスの挑戦」連載が開始。
徐々にコンテンツを整備して参ります。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ ■
■ 《早稲田大学WABOT-HOUSE研究所 展示・出版・催しなどのお知らせ》 ■
■ ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■《新着情報》
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
岐阜新聞の1月1日1面トップに「ロボット開発『歩み』加速」
今年の元旦、岐阜新聞1面に大きくロボットの記事が出ました。岐阜県の施
策としてのロボットの研究開発がテーマで、ギフ・ロボットプロジェクト21
の紹介、2005年3月開催の愛知万博への出展、知的クラスター創生事業に
ついての解説が掲載されました。そこに早稲田大学WABOT-HOUSE研究所も知的ク
ラスター創生事業に参加と紹介されました。
「世界に夢を発信」という小見出しも付けられ、ロボットと人間の未来とい
う我々のテーマについて、岐阜県とともに前進する姿が記された記事となりま
した。
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
中日新聞1月8日朝刊岐阜県版「明日へのおくりもの」に掲載
菅野所長のインタビューと、研究所の現況、今後の展望などについて掲載さ
れました。現在建設中の新棟(岐阜県ロボットプラザ(仮称))の模型画像も
載っています。記事では「(早稲田の研究している広範囲でのロボットの活用
は)地域としても活性化の起爆剤になり得る」とまとめられています。
#中日新聞Webにも掲載中。
http://www.chunichi.co.jp/00/gif/20040108/lcl_____gif_____006.shtml
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
連載『中央公論2月号(1月10日発売)「この都市のまほろば 美濃・岐阜」』
中央公論にて連載中の「この都市のまほろば」で1月号において岐阜がテー
マになります。その中では岐阜の地の成り立ち、そして岐阜の現在と未来につ
いて記されており、当研究所についてや岐阜におけるロボットについての記述
もなされ、そこにはロボットのメッカとしての岐阜が構想されています。
執筆は尾島俊雄副所長(早稲田大学理工学部教授)、絵は藪野健研究員(早
稲田大学芸術学校教授)が担当です。
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
岐阜放送テレビ「ハーイ拓さんの県政Q&A」にて研究所紹介
1月24日(土)18:00〜18:45に岐阜放送テレビで早稲田大学
WABOT-HOUSE研究所が紹介されます。
梶原拓岐阜県知事が出演の「ハーイ拓さんの県政Q&A」にて岐阜県の研究
開発のコーナーがあり、そこで菅野所長のインタビューが放映される予定です。
岐阜の皆様、どうぞご覧ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■《岐阜研究所ニュース》12月トピックス
12月は山川宏研究員(理工学部教授)による企業との連携活動で幕を開け
ました。各務原や可児の工業団地に所在の高い技術を持つ企業を何社も回り、
早稲田大学とともにロボットの制作をしてゆく企業との面談を行いました。
24日にはロボットと人間がともに暮らす「未来住宅」に関する研究報告会
を開催。未来住宅の像が徐々に明らかになってきました。
25日には岐阜研究所にて三輪研究室が中心となっての技術交流会を開催。
岐阜の地元企業の方においでいただき、会場では地域系の成果を紹介して参加
の皆さんからプロジェクトについての意見を頂戴しました。
この他ロボットの遠隔操作を視野に入れた広帯域ネットワークを活用しての
実験が岐阜〜東京間で繰り返し行われ、ロボットデザインについての活動や、
「ワボットのほん2」発行に伴う作業、岐阜のロボットについての広報関連の
会合なども目白押しで岐阜研究所は暮れの土壇場まで大忙しでした。
#これらを含めた岐阜研究所の活動内容は・・・
http://www.wabot-house.waseda.ac.jp/chiiki/news/index.htm
にて随時更新して掲載中です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■《WABOT−HOUSEコラム》
<<岐阜研究所新棟建築進捗状況・第二回>>
11月の終わりからスタートした新棟の建設工事は、天候や年末の繁忙期に
振り回されながらも、12月一杯で地下1階から1階の床になる部分までのコ
ンクリートを打ち終わり、2階へ繋がる柱も徐々に姿を現しはじめました。
年末は30日まで、年始は5日からというハードスケジュールの中、着々と
建設は進んでいます。今後天候不順等による遅れが無く順調に作業が進めば、
2月の終わりまでには建物の形は完成し、内装や仕上げ等の作業に入っていく
予定となっています。
(渋田 玲・早稲田大学WABOT-HOUSE研究所助手)
#研究所新棟についてはおよそ10日毎に建設作業を岐阜研究所ニュースにて
画像とともにお知らせしています。
http://www.wabot-house.waseda.ac.jp/chiiki/news/index.htm
#建築系グループの詳細については以下をご参照下さい。
http://www.ojima.arch.waseda.ac.jp/~wabot/
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
<<知能ロボティクスの挑戦・第一回 心の問題>>
「ロボットに心は生まれるのか?」いまやロボット研究において伝説となっ
てしまったテーマの一つです。なぜならこの問題を考える時、いきなり大きな
壁にぶち当たるからです。
そもそも「心」とは何なのか?、はたして我々人間でさえも「心」を持って
いると言えるのか?、確かに人間は悲しいときには泣くし、楽しい時には笑い
ます。これは心を持っているからだと説明できます。自分の隣にいる他人が心
を持っていることは、疑いのない事実であるかのように見えます。
しかしその所在を確かめようと他人の頭の中を覗いてみたらどうでしょう。
イオンの電位差により発生したパルスがピュンピュンと飛び交っているに過ぎ
ない。つまり隣の人はただの分子機械だった訳です。しかもそれは自分にもあ
てはまります。
「心」があると最も実感をもって信じていた自分もただの機械だった。では
いったいこの「心」なるもの、言いかえると「自己」「自分」はどこから来る
のか、そして機械が停止した後どこへ行くのか?、それはまだ誰にも分かりま
せん。
知能ロボティクスは脳科学、生物学、数理科学、認知科学、心理学などの諸
学問と結合しながら、このような哲学上の難問に迫ろうとしています。言葉で
語るのではなくモノを作ることをもって説明の方法とする。百聞は一見にしか
ず。このような方法をとることで、知能ロボティクスははたして人間を解明で
きるのか?この試みはまだ始まったばかりです。
(坂本 義弘・早稲田大学WABOT-HOUSE研究所助手)
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
《PR》
「ワボットのほん2」、もうお読みになりましたか?
人間とロボットの共生について、早稲田大学WABOT-HOUSE研究所の研究員が
交代で執筆するシリーズ第二巻が2003年12月に発行。橋本周司先生に
よる「ロボットを作る夢」というテーマ。
橋本先生が示す「私たちは次の新しい夢を見なくてはいけません」とは何な
のか。是非とも「ワボットのほん2」をお読みください。
岐阜、東京等の書店にて発売中です。また、岐阜県関連組織・学校には献本
を行っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■《リンク集》
今回はロボットに関連した日本語のページをご紹介しましょう。
知ってはいるけどもう少し詳しく調べたい、そんな時にこのリンク。
○(社)日本機械学会 http://www.jsme.or.jp/
○(社)日本ロボット学会 http://www.rsj.or.jp/
○(社)計測自動制御学会 http://www.sice.or.jp/
○(社)精密工学会 http://www.jspe.or.jp/
○(社)情報処理学会 http://www.ipsj.or.jp/
ロボットに関する分野は大変に広く、学会も多数あります。
ここでは代表的なものを挙げてみました。
○(社)日本ロボット工業会 http://www.jara.jp/
ロボット研究とロボット産業発展を目標とした組織。
ロボット関連の多くのリサーチを行っています。
○ROBODEX http://www.robodex.org/
「産業用ではないロボットの展示会」というコンセプト。
前回は2003年4月。次回はいつあるんでしょうか・・・?
○(独)理化学研究所 脳科学総合研究センター
http://www.riken.go.jp/r-world/research/lab/nokagaku/index.html
理研では脳科学の分野でロボットを扱っています。
○(独)産業技術総合研究所 知能システム研究部門
http://www.aist.go.jp/aist_j/research/research.html
産総研はロボット研究の盛んな組織で他の部門でも研究が行われています。
○ソニー QRIO
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/QRIO/
早稲田との繋がりも深いSDRプロジェクトのページ。
○本田技研 ASIMO
http://www.honda.co.jp/ASIMO/
ご存じホンダのASIMO。ASIMOってレンタルしてるのご存じですか?
○早稲田大学ヒューマノイド研究所
http://www.humanoid.waseda.ac.jp/index-j.html
前回も掲載しましたがもうご覧になられましたでしょうか。
「早稲田ロボットの歩み」のページは必見。是非是非。
○日本のロボット研究
http://robotics.aist-nara.ac.jp/jrobres/index-j.html
奈良先端科学技術大学院大学にある、日本全国のロボット研究を行う研究機
関等のリンク集。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■《編集後記》
この正月休みに目を通した資料の中に花森安治に関する書籍がありました。
読みつつ考えたのは、自動車を初めとした工業製品や食品の品質に厳しい目を
向けた彼が、果たしてロボットをどのように見つめたであろうかということで
す。消費者の安全と安心、そして生産者の責任というものに早く着眼した彼の
スタンスは我々の考えるロボット像にも十分につながるものがあります。
先端技術の粋としての存在であるロボットが、人間の生活に寄り添うロボッ
トへと変わりつつある現在、ロボットのイメージを考えるに際してそのミクロ
からマクロに至る様々な像をデザインする段階に前進しつつあると思います。
岐阜の声を、そして岐阜の地が持つ知恵を早稲田のロボットに融合させてゆ
く術を、岐阜研究所駐在のスタッフがそれぞれに試行錯誤しつつ探して具体化
に向かっています。
早稲田大学WABOT-HOUSE研究所メールニュース第2号、いかがでしたでしょう
か。メールニュースで扱ってほしい内容などありましたらどうぞお知らせくだ
さい。今後も早稲田大学WABOT-HOUSE研究所岐阜研究所と岐阜を初めとした全国
の皆さんとの橋渡しが出来ればと思っています。
(小笠原 伸・早稲田大学WABOT-HOUSE研究所講師)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【早稲田大学WABOT-HOUSE研究所メールニュース 第2号】2004/01/09発行
======================================================================
▼新たに配信(または配信中止)を希望される方はお名前、年齢、御所属企業
・機関名、送付希望メールアドレスを記入の上、以下のメールアドレスへお送
り下さい →mailnews_admin@wabot-house.waseda.ac.jp
======================================================================
▼早稲田大学WABOT-HOUSE研究所へのご意見・ご質問、さらに当研究所との技
術連携などをご希望の場合などは以下のメールアドレスへお送り下さい。
→wabot-house@list.waseda.jp
======================================================================
◎研究所公式ホームページ:http://www.wabot-house.org/
◎早稲田大学ホームページ:http://www.waseda.ac.jp/index-j.html
======================================================================
編集人:小笠原 伸(早稲田大学WABOT-HOUSE研究所講師、
岐阜研究所コミュニケーション・ディレクター)
発行元:早稲田大学WABOT-HOUSE研究所 岐阜研究所
〒509-0108 岐阜県 各務原市 須衛町 4-179-1
テクノプラザ本館 106号室
電話:0583-79-2223 Fax:0583-79-6061
Copyright(C) 2004 WABOT-HOUSE Laboratory,Waseda University
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(送付したメールニュースに一部誤記があり、修正した版を掲載しています)